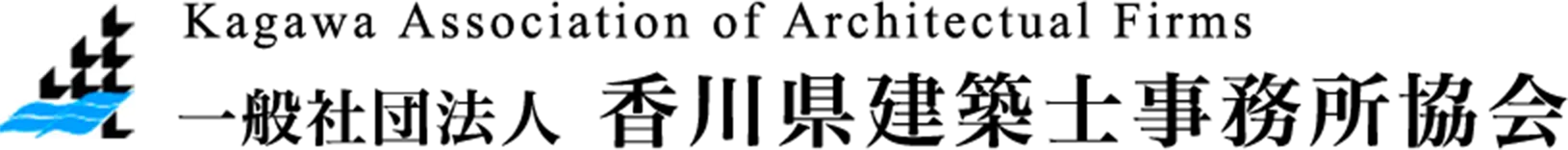協会について
寄稿
社内研修旅行記(オーストラリア編)

(株)清和設計事務所
令和5年に社内研修旅行として訪問したメルボルンとシドニーの旅行記を報告します。昨今の旅行代金の高騰もあり、当初ヨーロッパ5泊7日を企画していましたが、コロナ前の予算で行けるのが2泊5日のオーストラリアでした。
初日は、夕方まで東京の建物視察をしました。羽田から貸し切りバスで代々木体育館まで行き、コープオリンピアの南国酒家でランチをしました。表参道をフリー散策し根津美術館で集合しました。参加者は事前に見たいところをリサーチしていたようで、それぞれ路地の奥までスター建築家の作品群を巡っていました。その後、六本木の国立美術館、ミッドタウン、21-21designを視察し、麻布台ヒルズを横目に空港に向かいました。

夜羽田から飛び立ち、機中泊で2日目の朝、メルボルンにやってきました。最初に訪れた王立展示館は、1880年に開催されたメルボルン万国博覧会のために建設され、オーストラリア最初の西洋建築としてルネッサンス・ビザンツ・ロマネスクなど多様な様式を組み合わせた建築です。

昼食はメルボルンで定番のスパークリングワインを片手にパスタを食し、現代美術センター(ACCA)、セントパトリック大聖堂、フェデレーションスクエアに立ち寄りました。フェデレーションスクエアは欧風建築スタイルの多い街並みの中で、現代建築感あふれる空間で気持ちも上がる気がしました。

そこからは徒歩で、フリンダーストリート駅を見て、メルボルンのまちの象徴でもあるロイヤルアーケードとブロックアーケード街を散策しました。国内でも最も長いアーケード街で、欧風デザインにガラスを多く取り入れた屋根が連続する様子は圧巻でした。また、商店街にあるメルボルンセントラルの建物は黒川紀章が設計し、当時世界でも最大級のガラス屋根だったようです。

その後、世界で最も美しい図書館の一つとされるビクトリア州立図書館と旧メルボルン監獄を視察しました。日本でも図書館の秀逸な建築作品が多くなってきていますが、その原点ともいうべき建築でした。

メルボルンはもともとオーストラリアの中心都市として発展してきただけに、特徴的な伝統的な建築空間群と現代建築が混在する魅力的な都市だと感じました。
その後、疲れを癒す間もなく空港に向かい、空路シドニーに移動し、ホテルにチェックインしました。

3日目はシドニーの視察です。まずはオペラハウスとハーバーブリッジのビューポイントでもあるミセスマコリーズ・ポイントに行き、ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館を見学しました。この美術館はSANAAの設計です。ガラスファサードがSANAAらしい洗練された空間になっています。写真を撮るのが難しかったのですが東側の入り組んだガラスの段々畑のような外観は圧巻です。

その後、セント・メアリー大聖堂に立ち寄り、ランチの後、いよいよメインの世界遺産シドニーオペラハウスの視察です。設計者はヨーン・ウッツォンが国際コンペで選ばれましたが、設計途中で設計を外れており、デザインはそのまま踏襲されたが、ウッツォンは完成を見ることはなかったとのことです。

球体を切り出したパーツを組み合わせた外観は、実際に見るとスケールの大きさと羽ばたくような形状が深く印象に残りました。この日はオペラハウス50周年の記念イベントがあり、偶然にも全館が開放されて視察できるという幸運な日でした。メインホールでは、世界でも最高クラスのパイプオルガンをずっとデモ演奏してくれていて、涙を流す参加者もいました。
夕食後はロックス地区ハーバーまで散歩し、オペラハウスのライトアップを楽しみました。大型客船も停泊し、世界的な港のにぎやかさを感じました。

4日目もシドニーを回ります。まず、ワンセントラルパークの最新マンションを見ました。光庭を照らすダイナミックな反射板が、デザイン的にも圧倒的な存在感を創出しています。シドニー工科大学では、フランクゲーリー設計の変化に富む奇抜ともいえる建築を視察しました。


その後、隈研吾氏設計のダーリング・エクスチェンジ図書館に行きました。曲線の籐のかごのようなデザインは、繊細でどこか和風感を感じさせる建物です。

ダーリングハーバーで洗練された最新の建物群を見ながらランチをした後、シドニー現代美術館やクイーンビクトリアビルディングの伝統建築デパートなどを回りました。そして、夜の便で日本に向かい5日目の昼前には帰宅しました。まあまあハードでした。
シドニーは港湾と調和するオペラハウスの圧倒的な存在感を核に、挑戦的な現代建築が次々と整備される活力ある都市だと感じました。
この研修旅行は数年に一度実施しています。すでに世界3大ゴシック教会も制覇していますが、まだまだ行きたいところが多くありますので、仕事も頑張りたいと思います。